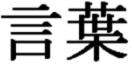
[ 01, メモリー ]
「誰だ、手前ェ」
眉に皺を寄せて、こちらを睨んでいる整った顔をした青年を見た。(いや、まだ少年かな)どくん、と心臓が波打つ。
「何言ってんの、リボーン」
「…リボーン?誰だ、それ」
とりあえず、俺はこの状況についていけていないことは確かだ。第一に、リボーンが俺と会話をしている。そんな事あった試がない、ような気がする。多分。
「やれやれ、ふざけてるの」
「手前は誰かって聞いてんだッ」
「俺はランボだ!あんた頭可笑しくなったんじゃないの?!」
リボーン、が。あのリボーンが怒鳴ってる。そんなのって、ありえない。だいだい俺に感情を表すなんて。ああもう、信じらんない。いったいどういう状況なわけこれ!誰か助けてよ!…頭が、可笑しくなった。無意識に口走った言葉を脳内で半濁する。…もしかして。いや、ありえないよ。だってリボーンだよ?あのリボーンが、そんなドラマじゃあるまいし。そんな馬鹿なことって、ない、よね。
嫌な予感がチリチリと脳髄を焼く。
「………何処だ、ここ」
「ねえ、リボーン。…もしかして、」
リボーンが不思議そうに辺りを見回した。別人に、見える。俺には。いつも纏っていたあの痛いほどのオーラみたいなものがまったく、ない。
「リボーン、」
「だから、リボーンって誰だ」
「…覚えてないの?」
自分の声が、やけに震えているのを知る。…こんなリボーン、見たくない。震えだしそうになる手足を必死で押さえ込む。
「何を」
「リボーン、って。あんたの名前だよ」
「俺の?…………」
リボーンが、ぎゅっと掛けられたシーツの端を握るのが見えた。青白い顔が下を向く。
「俺はランボだ。ここは病院」
「……俺は、…………リボーン?」
「そうだよ、ねえ、あんた本当に覚えてないの」
「………」
声が震えだす。リボーンが小さく首を左右に振って、唇を咬んだ。ありえない、リボーンが。そんなのって、ないよ。信じられない。
「ねえ、あんたは本当に本当に覚えてないの。何も覚えてないの」
「……………」
「あんたはリボーンだ。あの、最強のリボーンだよ?」
「……………」
「ねえってば!」
「うるせえ!」
いつのも声で、いつもの顔でどなってるはずなのに。全然違う。俺の知ってる、あの傍若無人で最強無敵なヒットマンの面影はない。ねえそんなのって、ないよ。…俺が、そんなの俺のせいじゃない。
目の前がふいに真っ暗になった気がした。リボーンは置いてけぼりにされた迷子みたいな顔で上半身を起こしたまま、ずっと正面を見ている。
「…何にも、思い出せねえ…?」
自分自身に問いかけるように、リボーンの頼りなげな声が響いた。
「…自分が誰か、分かる?」
「…………」
「じゃあ、どうしてここにいるのかは」
「…………俺は、」
まるで見えないものから身を守るように、リボーンが自分自身に手を回した。少し震えている。……あんたは、最強のヒットマンじゃないの。凄腕のヒットマンでしょ?何で、そんなことぐらいで震えてるの?……そんなのって、ないよ。
がちゃり、と背後の扉が開く音。
「なんか声聞こえたけど。どうしたの?」
「………ツナ、さん」
「あ、リボーン。目、覚めたんだ。どう調子は。腕痛い?」
リボーンが弾かれたように振り返った。ツナさんを見て、奇妙な表情をつくった、と同時にツナさんが伸ばした手を、パシッと弾く。
「どうかしたの?リボーン」
「…ツナさん、」
震えている、情けない声。
「リボーン、何にも覚えてない」
「…どういうこと」
「自分の名前とか、何にも。俺が誰かも」
「本当に?」
こくり、と頷く。ツナさんが眉を顰めて、リボーンのほうを向いた。
「リボーン、俺が誰か分かる?」
「…………」
「俺は、ツナ。沢田綱吉だ。お前の教え子」
青白い顔で、またリボーンが首を左右に振った。ぎゅうっとさらに強くシーツを握る。見たくない。
「…教え、子?」
リボーンの声が震えている。そんなの、聞きたくない。
「そう。教え子だよ、お前の。リボーン、本当に何も思い出せない?」
「……俺は、リボーン」
「うん、お前はリボーン」
「ここは、病院」
「………思い出せないんだね」
大丈夫だ、という風にツナさんがリボーンの頭をぽんぽん、と撫でるのが見えた。俺は本格的に、パニックを起こしそうな手足をまた必死で押さえ込む。ねえ、そんなのってないよ。嘘だっていってよ、俺のせいだ。全部俺のせいだ。
ぽんぽん、と頭に手の感触がする。顔を上げれば、ツナさんがふんわりとほほえんでいた。
「ランボのせいじゃないよ」
「……俺のせいです」
困ったような顔をした後、急にボスとしての顔に戻った。傍に医師を控えさせた、獄寺さんに視線を飛ばす。
「困ったことになったよ獄寺くん」
「ええ、…まさか、あのリボーンさんが」
「いくら最強だろうと、リボーンも人間だからね。…専門家に任せよう」
そういって、医師の肩を叩いた。恭しく礼をし、医師がまだ呆けたようにあらぬ方向を見ているリボーンの方に向かう。
「ランボ、出よう」
「……はい」
もう一度後ろを振り返る。医師の影でリボーンがよく見えない。………聞こうと、思ったのに。
…ねえ、あの時あんたは、どうして?
>>02
拍手